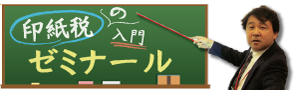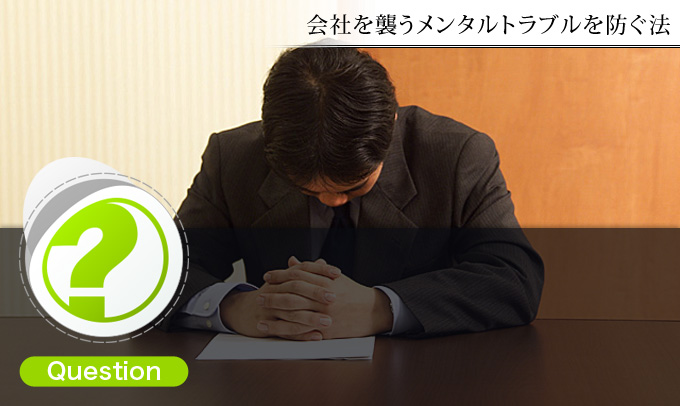
メンタル不調で休職中の社員から、「リハビリを経ての復職が可能である」という内容の主治医の診断書が提出されました。当社ではこれまでリハビリ出社という対応をしたことがないのですが、どのようにすればよいでしょうか。

リハビリ出社を実施することで社員の円滑な復職に役立つと判断できる場合、または、復職の可否を判断するために有益である場合には、休職中の社員と書面で合意書を作成し、位置づけを明確にしたうえで、リハビリ出社を実施しましょう。
そもそもリハビリ出社とは?
リハビリ出社について規定した法律は今のところありません。そのため、明確な定義はありませんが、一般的には、「休職期間中に、職場復帰の可否の判断や、円滑な職場復帰の準備等の目的で、本来の職場などに一定期間継続して試験的に出社すること」を指します。
なお、厚労省の定めた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(改訂版)」には、「試し出勤制度等」という名称で、次の3つの例が紹介されています。
- ① 模擬出勤
- 職場復帰前に、通常の勤務時間と同様な時間帯において、短時間又は通常の勤務時間で、デイケア等で模擬的な軽作業やグループミーティング等を行ったり、図書館などで時間を過ごす。
- ② 通勤訓練
- 職場復帰前に、労働者の自宅から職場の近くまで通常の出勤経路で移動を行い、そのまま又は職場付近で一定時間を過ごした後に帰宅する。
- ③ 試し出勤
- 職場復帰前に、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。
リハビリ出社を行う場合、どんな注意点が必要か?
前述のとおり、リハビリ出社について規定した法律はありません。したがって、会社がリハビリ出社制度を導入する法的義務はなく、実施するか否かは会社の裁量に任されています。
もっとも、主治医の診断書に「リハビリを経ての復職が可能」とある以上、会社としては、リハビリをさせずに社員を復職させることには抵抗があるでしょう。
そこで、リハビリ出社を行う場合の注意点について説明します。重要なことは、リハビリ出社の内容について、社員と書面で合意をしておくか、または、「リハビリ出社規程」等の形式で制度化し、位置づけを明確にすることです。
特に、次の事項については、必ず明確にしておきましょう。
(1) 休職期間中の制度であること
リハビリ出社は、あくまで円滑な職場復帰の準備のための制度であり、勤務ではありません。あくまで休職期間中に実施するものです。この点を必ず明確にしておきましょう。
(2) 賃金を支払うかどうか
リハビリ出社は、あくまで休職期間中に実施するものですから、必ずしも会社が賃金を支払う必要はありません。裁判例でも、リハビリの作業内容が簡易であったことや、リハビリ出社期間中の出退勤の管理がなかったことなどを理由として、リハビリ出社期間中の作業が労務の提供に当たらないとしたものがあります(西濃シェンカー事件・東京地裁平成22年3月18日判決・労判1011号73頁)。
したがって、会社がリハビリ出社期間中の賃金を支払わないという合意をすることも可能です。
もっとも、リハビリ出社の内容として、短時間であっても会社の業務に従事させる場合などには、労務の提供に当たり、賃金を支払わないことが違法とされかねませんので、注意が必要です。
(3) 労災の適用について
リハビリ出社期間中に労働災害が発生した場合、労基署は、賃金の支払いの有無をもって労災適用の有無を判断することが多いようです。したがって、会社がリハビリ出社期間中に賃金を支払わない場合は、労災の適用がないことについても明確にしておくべきです。
また、労災の適用がないため、会社の裁量で任意保険をかけることも検討しておきましょう。
なお、労災の適用の有無はあくまで労基署が判断するものであり、会社と社員の合意により決められるものではありませんが、会社のスタンスを明確にしておくことは重要であるといえます。
まずは診断書を作成した主治医のヒアリングを行う
会社はメンタル不調について専門的なことはわかりません。他方、主治医は、会社の事業内容や休職中の社員の就労環境についてよく知らないことが一般です。
産業医がいればその意見を聞くべきですが、いない場合は、リハビリ出社の内容、期間、相談体制等について、主治医のヒアリングを行い、意見をよく聞きながら実施することが大切です。
これにより、不適切なリハビリによって病状をかえって悪化させる事態を避けることができます。