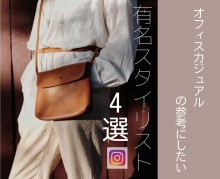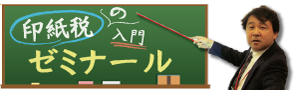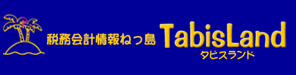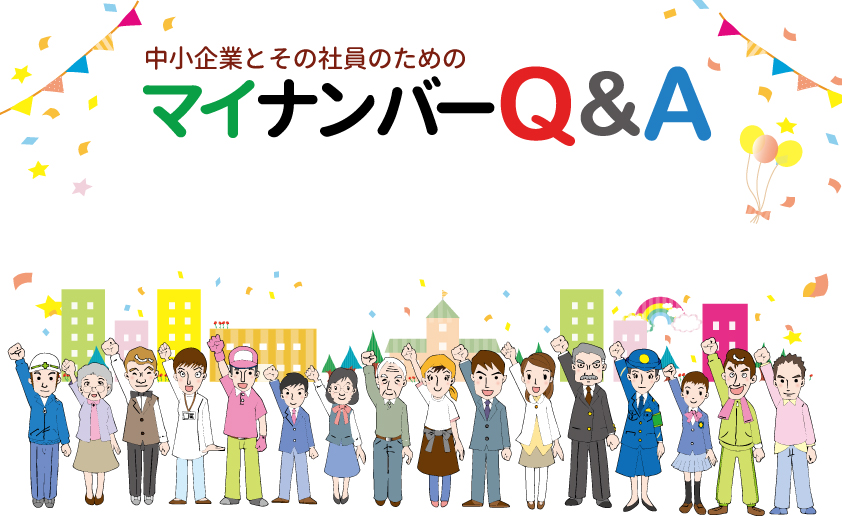
アルバイトからマイナンバーを取得するときに注意することは?
 大学生をアルバイトとして雇っています。アルバイトからも、マイナンバーを取得しなければならないのでしょうか。外国人留学生のアルバイトも同じでしょうか。また、取得の際にどのように説明をすればよいでしょうか。
大学生をアルバイトとして雇っています。アルバイトからも、マイナンバーを取得しなければならないのでしょうか。外国人留学生のアルバイトも同じでしょうか。また、取得の際にどのように説明をすればよいでしょうか。

 パート・アルバイト社員からもマイナンバーを取得する必要があります。
パート・アルバイト社員からもマイナンバーを取得する必要があります。

 パート・アルバイト社員からもマイナンバーを取得する必要があります。
パート・アルバイト社員からもマイナンバーを取得する必要があります。
雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。
アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。
すでに採用している者に対しても、いつ、どのような形で取得するかを決めておくとよいでしょう。
他にも、学生のアルバイトについて予想される点としては、通知カードの問題があります。
平成27年10月以降、マイナンバーを国民に通知するため、各市区町村から世帯ごとに通知カードが送られます。この通知カードは、住民票の住所地に送られることとなっています。
そのため、住民票を実家から移していない一人暮らしの学生の方は、自分の番号を知らないことも予想されますので、余裕をもって取得に向け動くことが必要です。
 マイナンバーは「住民票を有するすべての人」に通知されます。
マイナンバーは「住民票を有するすべての人」に通知されます。

 マイナンバーは「住民票を有するすべての人」に通知されます。
マイナンバーは「住民票を有するすべての人」に通知されます。
中長期在留者や特別永住者などの外国人の方は、住民票を有しています。住民票を有している以上、マイナンバーが割り当てられ、通知がなされます。
ですので、外国人留学生のアルバイトも、同様の取扱いをする必要があります。
 取得の際には、利用目的の特定、通知等が必要となります。
取得の際には、利用目的の特定、通知等が必要となります。

 取得の際には、利用目的の特定、通知等が必要となります。
取得の際には、利用目的の特定、通知等が必要となります。
特に短期契約のアルバイトの場合など、マイナンバーを会社に教えることを戸惑う方がでてくることも予想されます。
ですので、あらかじめ、取得事務担当者が、マイナンバーを取得する目的や、何に利用されるかを、わかりやすく説明できるよう、今のうちから準備しておくことをお勧めします。
マイナンバーの取得の際には、利用目的を特定し、通知または公表しなければなりません。
ガイドラインでは、
「本人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する必要がある」
とされています。ですので、例えば「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」といった形で、利用目的を特定し、従業員に通知または公表する必要があります。
会社がマイナンバーを取り扱うことができるのは、原則として、源泉徴収票や支払調書といった書面を行政機関に提出する場合に限られます。
これ以外の目的で、会社が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を第三者に提供することや、保管し続けることは認められていません。
円滑にマイナンバーを取得するためには、こういったことまで従業員に伝える必要があるでしょう。
- ▼連載「中小企業とその社員のためのマイナンバー対応Q&A」
-
- 第12回 安全管理措置などの義務が守れそうにありません!
- 第11回 社員からマイナンバーの提供を受けるときの「本人確認」って?
- 第10回 そもそもマイナンバー制度を始めた目的は?
- 第9回 もしもマイナンバーの提出を拒否されてしまったら?
- 第8回 法人番号とは何? どんなときに使うものなの?
- 第7回 採用内定者や派遣社員からマイナンバーを取得するタイミングはいつ?
- 第6回 クラウドサービスを使って収集・保管するときに気をつけることは?
- 第5回 社員などから集めたマイナンバーを管理するうえでの注意点は?
- 第4回 マイナンバーについて、いつまでに、どのような内容の従業員教育が必要?
- 第3回 もしも、マイナンバーを漏えいさせてしまったら?
- 第2回 アルバイトからマイナンバーを取得するときに注意することは?
- 第1回 マイナンバー法は、すべての事業者に関係する法律なの?