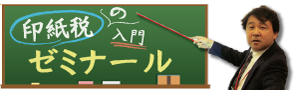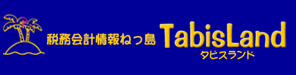宣伝であることを伏せて、新商品を紹介する記事を書くことに問題はありますか?
宣伝であることを伏せて、新商品を紹介する記事を書くことに問題はありますか?

- 質問者
-
私は、最新の化粧品や美容家電などが大好きで、主に新商品の紹介・レビューをするサイトを運営しています。長いこと続けてきたかいもあって多くの方のアクセスがあります。
最近、某化粧品会社から、「新商品を紹介する記事を書いて欲しい」という連絡をいただきました。ただし、会社から頼んだことは伏せて欲しいと言われているのですが、引き受けてしまってよいものでしょうか?
- 弁護士
-
いわゆるステルスマーケティングの問題について検討する必要がありますね。
- 質問者
-
ステルスマーケティング…巷でよく「ステマ」と呼ばれるものですね。
ステマって何が問題なのでしょうか? - 弁護士
-
まず、ステルスマーケティングとは、宣伝であることを隠して宣伝を行うマーケティング手法をいいます。
通常、消費者は、宣伝であるとわかっていれば、その内容・表現が誇張されたものであることを差し引いてみることで、商品の価値・性能を正確に判断しようとします。
しかし、ステルスマーケティングがされてしまうと、消費者が宣伝に対して払うべき注意をすることができず、商品の価値・性能に関して正しい判断ができなくなってしまうという問題があります。 - 質問者
-
私も、美容系の有名ブロガーさんが良い評価をしている新商品は信用して買ってしまうことが多いのですが、もしかしたらステマだったのかもしれません…。だとしたら、ちょっと悔しいですね。
それでは、ステマを禁止する法律はあるんでしょうか?
 宣伝であることを隠して宣伝をするだけの行為を直接取り締まる法律はありません。
宣伝であることを隠して宣伝をするだけの行為を直接取り締まる法律はありません。

- 質問者
-
えっ? それだとやりたい放題になってしまいませんか? もう何を信じてよいのかわかりません…。
- 弁護士
-
話にはまだ続きがあります。
宣伝であることを隠すというにとどまらず、商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような記事を書くこと等については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)において禁止されています。
詳しい内容は、景品表示法の5条を読んでみてください。第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの簡単に説明すると、
「実際にはそうでもないのに、とても良い品質だと思わせる表示をしてはいけない」
と定められています。
 あまりにも実態とかけ離れた感想を掲載することは禁止されているわけですね。
あまりにも実態とかけ離れた感想を掲載することは禁止されているわけですね。

- 質問者
-
少し安心しました。でも、この景品表示法は、商品を提供する事業者の不当表示しか禁止していないのではないですか?
- 弁護士
-
鋭い指摘ですね。たしかに、記事を掲載した人が商品を提供する事業者でなく、他人の商品を推奨するだけの立場にしかない場合は、原則として、景品表示法の規制を受けることはありません。
また、景品表示法は、違反したからといって直ちに刑事上の責任を追及されるわけではなく、違反行為について当局による行政処分を受け、これに従わなかった場合にはじめて刑罰の対象となります。
もっとも、宣伝した商品がいわゆるインチキ商品で、商品を売ること自体が詐欺に当たるような場合に、企業の宣伝に協力してこのような商品を推奨してしまうと、詐欺の幇助として民事上、刑事上の責任を追及される可能性がありますので、注意が必要です。
- 質問者
-
なるほど。ステマの問題点について整理できてきた気がします。
そうすると、今回は新商品を紹介するように頼まれただけなので、自分なりの感想を掲載するだけなら特に問題はなさそうですね。
 違法ではないからといって、問題がないとは言い切れません。
違法ではないからといって、問題がないとは言い切れません。

- 弁護士
-
ちょっと待ってください。たしかに、法律上の問題が起きる可能性は低いでしょうし、自分の感想を書くだけなら、商品の内容について嘘をついていることにはならないでしょう。
しかし、宣伝であることを隠すステマは、違法ではないとしても、社会的に問題のある行為であるとの認識が形成されており、非難の的になりやすく、いわゆる炎上に結びつく危険性が高い行為であることに違いはありません。
そして、一度「ステマをした」という評価がされてしまうと、レビューサイトとしての信用を回復するのは難しいものと考えられます。また、企業の側からしても、ステマをした企業というレッテルがつきまとうことになり、真に肯定的なレビューがあったとしても、「またステマだろう」と正当な評価を受けることが難しくなってしまいます。
ですから、企業の依頼で商品の紹介をする場合は、どちらの立場からしても、「ステマをした」という非難を受けないように、企業からの依頼であることを明らかにしておくべきでしょう。
- 質問者
-
事実上のリスクを減らすためには、企業からの依頼であることを明記することが大事なんですね。その表現方法については工夫してみます。
- 弁護士
-
商品の宣伝に協力する場合は、法律上問題となるような表現をしないのは当然ですが、信用低下問題のほうが現実化しやすいので、事実上のリスクも意識することが重要です。
- ▼連載「弁護士が教える「ネットの法律&マナー」講座」
-
- 第11回 「プライバシー権の侵害」とは? 店内の様子をブログに投稿する際、どんな注意が必要か?
- 第10回 街中で人気アーティストに遭遇! スマホで撮った写真をブログにアップしても問題ない?
- 第9回 顧客の購買情報など「ライフログ」を取得・利用したい。どんな点に注意が必要?
- 第8回 知人のコンサートや試合の動画を投稿するときも、著作権や肖像権が関係してくる?
- 第7回 ネット上で素敵な写真を見つけました。自分のサイトに転載してもいい?
- 第6回 他社の商標を“検索連動型広告のキーワード”や“メタタグ”に使いたい…
- 第5回 どんなケースが「肖像権の侵害」に? 具体的に気をつけるべきポイントは?
- 第4回 ステマに注意! 企業から頼まれて商品レビューを書く場合に気をつけたいこと
- 第3回 告訴されることも! ネットへの書き込みで刑事上の責任を問われる場合とは?
- 第2回 ブログで他人の著作物を引用したり、「まとめサイト」を作ることに問題はない?
- 第1回 著作権とは何か? ネットで情報を発信するとき、どんな注意が必要か?